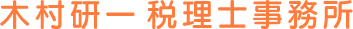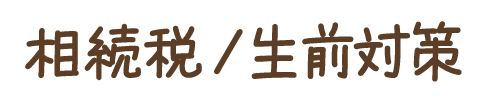

- TOP
- 相続税/生前対策
相続税とは?
相続税は、亡くなった方が所有していた財産を家族などが受け継いだ際に、その財産に対してかかる税金です。不動産や預貯金、株式などを配偶者や子どもが相続する際、一定の金額を超えると課税対象となります。 この相続税には、単なる課税というだけでなく、「富の再分配」という社会的な役割もあります。
資産の多い家庭に生まれた人だけが多くの財産を受け取ることがないように、相続税を通じて富の偏りを調整し、経済的な格差を抑える仕組みとなっています。 相続財産の一部を税として納めることで、社会全体への還元を図るという考え方が背景にあるのです。
相続税は生前の準備が重要です
相続税の対策は、相続が発生してからではできることが限られるため、生前のうちにしっかりと準備しておくことが大切です。早めに備えておくことで、ご家族の負担を軽減し、安心して相続を迎えることができます。
相続税の申告期限と注意点
相続税の申告は、亡くなった方のことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などがかかる場合があるため、注意が必要です。
申告期限までに遺産の分割ができなかったら?
遺産の分割が相続税の申告期限までに決まっていない場合でも、申告の期限そのものが延びることはありません。そのため、ひとまず法律で決められた相続の割合(法定相続分)に沿って、各相続人が財産を受け取ったものとして申告・納税する必要があります。 ただし、この段階では「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった税金を軽くする特例が適用されません。これらの特例は、原則として遺産の分割が完了していることが条件となるためです。
なお、申告期限から3年以内に正式な分割が完了すれば、申告をやり直すことで特例を適用できる場合もあります。 このように、まずは10か月以内に一度申告を行い、その後分割がまとまった時点で、必要に応じて修正や再申告を行うという流れになります。
京都市右京区で相続税対策を検討中の方へ
- 自分に相続税がかかるのか、確認する方法は?
- 相続税を減らすためにどんな対策が有効なのか?
- 相続の手続きはどこから始めるべきか?
- 相続税の税務調査を受ける際に、何に注意すべきか?
- 自宅や不動産など、特定の資産をどのように相続させるべきか?
京都市右京区の木村研一税理士事務所では、相続税対策をお考えの方に向けてお客様一人ひとりの状況に合わせたきめ細かなサポートを行っています。 当事務所の特徴は、税額を減らすだけでなく、相続をめぐるご家族間の争いを防ぐ「円満な相続」の実現にも力を入れている点です。
遺言書の作成や財産の分割方法に関するアドバイスを通じて、将来のトラブルを防ぎ、円満に遺産相続を進めるための具体的な提案をいたします。
初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続税の申告・贈与・生前対策など、当事務所のサポート内容
相続税対策
当事務所では、まず相続税がどれくらいかかるのかをシミュレーションし、その結果に基づいて最適な節税対策をご提案します。相続税は、財産の額が増えるほど税率が高くなり、最大で55%に達することもあります。そのため、財産をどう分けるのが最適か、遺言書をどう作成すべきかなど、具体的なアドバイスを提供いたします。
-
相続税のシミュレーション

相続税がどの程度かかるのか、事前にシミュレーションを行うことで、最適な対策を明確に把握できます。お客様の財産内容に基づき、相続税の予測を立て、最適な節税方法をご提案します。
-
小規模宅地の特例活用

土地を相続する際、相続税を50%〜80%軽減できる「小規模宅地等の特例」を活用することができます。この特例は、亡くなった方の自宅や事業用地に適用されます。当事務所では、特例を最大限活用できるように土地評価を見直し、税負担を大きく軽減する方法をサポートします。
-
不動産の活用による評価額引き下げ

現金や預貯金などの資産は、その額面通りに評価され、相続税の課税対象となります。しかし、これらの資産を不動産に換えることで、評価額を引き下げることができます。例えば、現金や預貯金をマンションや土地などの不動産に換えたり、土地に賃貸アパートを建てて「貸家建付地」にしたりすることで、評価額を抑えることができる可能性があります。
-
生命保険を活用した負担軽減

生命保険の受取金は一定額まで相続税が非課税となり、特に相続人が多い場合に効果的です。適切な保険金額を設定することで、相続税支払いの資金を準備し、相続人間での負担を分散することができます。
-
資産の分割方法を最適化

相続税の負担を減らすためには、財産の分け方が非常に重要です。遺産分割の方法によって、相続税の額が大きく変わるため、相続人の年齢や生活状況を考慮して、最適な分け方を決める必要があります。特に、特定の相続人に優遇措置をとる場合は、専門家と相談しながら慎重に決定することが大切です。
贈与に関する手続き
生前贈与は、将来の相続税負担を軽減するために効果的な方法です。年間110万円までの贈与は非課税となるため、この枠を活用して相続税を節税することが可能です。
贈与を行う際には、贈与証書や贈与税申告書を作成する必要があります。手続きが不適切だと、非課税で贈与したつもりでも課税対象となることがあります。 そのため、相続税の節税対策として贈与をうまく活用するためには、税理士に相談し、計画的に進めることが大切です。
相続発生後の手続きと申告
相続が発生した場合、まずは戸籍を取得して相続人を確認し、法務局で法定相続情報一覧図を作成します。これにより、銀行手続きや不動産登記がスムーズに進みます。その後、相続財産や負債を把握し、相続税の評価を行います。
評価後は、相続人全員で財産の分け方や相続税額を相談し、遺産分割協議書と相続税申告書を作成します。署名・押印後、申告書を提出し納税となります。 当事務所では、税理士による「書面添付制度」を適用し、税務署の指摘を受けにくくしています。これにより、申告後の安心も提供いたします。
無料相談の流れ
木村研一税理士事務所では初回相談を無料で承っております。
相続税に関するお悩みをお持ちの方々に、まずはお気軽にご相談いただけるように、費用を一切いただいておりません。どんな小さな疑問でも遠慮なくお聞きいただけますので、まずは無料相談をご利用ください。
-
1.ご予約
まずはお電話やメールで、木村研一税理士事務所にご連絡ください。ご相談内容を伺い、無料相談の日時を決めさせていただきます。
-
2.ご来所
ご予約いただいた日時に当事務所へお越しください。事前に相談内容に関する資料をご持参いただければ、より具体的なアドバイスが可能です。
-
3.ヒアリング
税理士がご相談者様のお悩みやご希望をしっかりとお聞きします。気になることや不安な点は、遠慮せずに何でもお尋ねください。
-
4.サポート内容のご案内
お話をお伺いした後、当事務所が提供できるサポート内容を具体的にご案内します。また、サービスにかかる費用の目安についてもご説明いたします。
-
5.ご依頼
サポート内容や費用にご納得いただけたら、ご契約を進めます。無料相談の際に契約を決める必要はありませんので、じっくりご検討いただき、後日ご連絡いただいても構いません。
-
6.サポート開始
ご契約後は、お客様の頼れるパートナーとして、全力でサポートを始めます。どんなことでもお気軽にご相談ください。